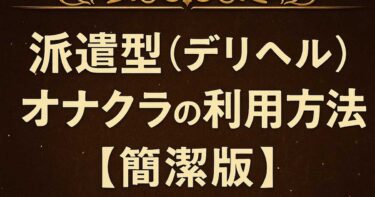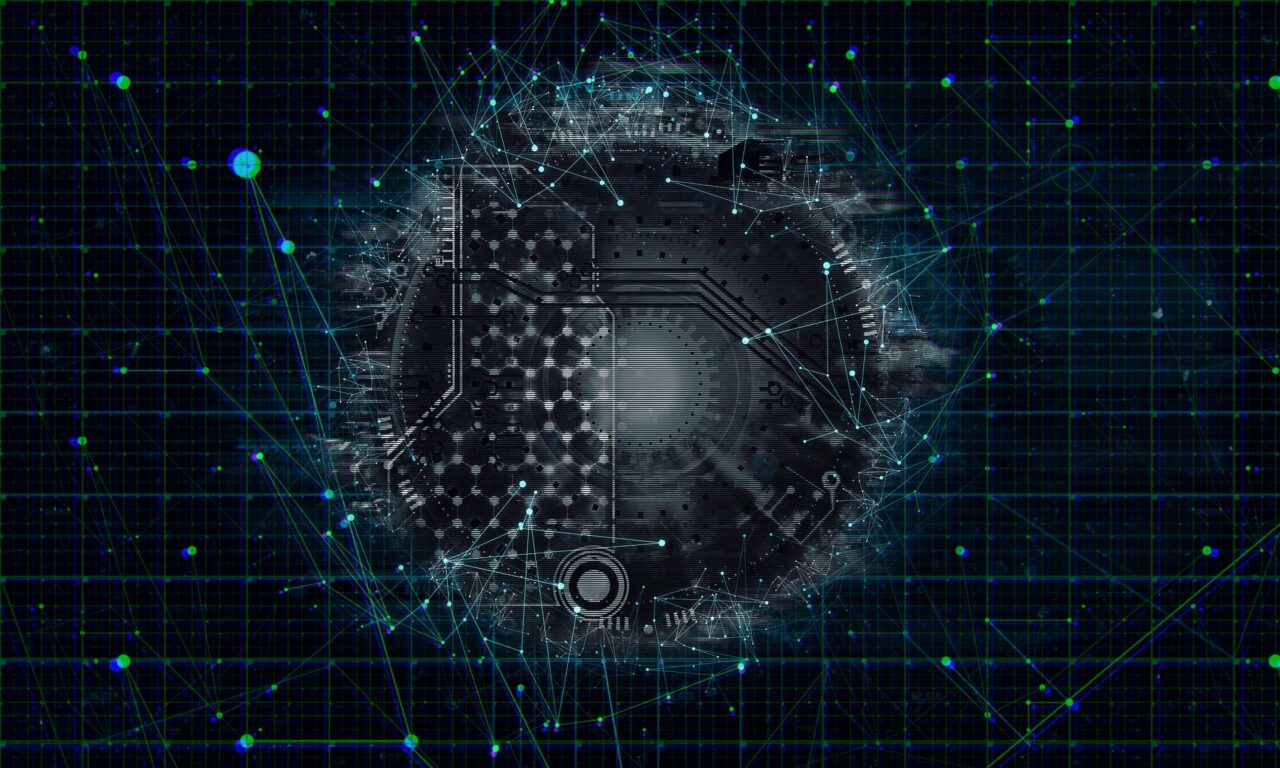「夜の扉」
仕事に追われる日々の中、俺は完全に疲弊していた。33歳になり、会社の中では中堅社員という立場だが、心の中は空虚だった。終わりの見えない業務、上司からの無言のプレッシャー、そして家に帰っても何も変わらない、ただ時間だけが過ぎていく日常。そんな生活が続き、いつの間にか笑顔も消え、自分が何のために働いているのかさえ分からなくなっていた。
その日は特に酷かった。朝からクレーム対応に追われ、残業をしても終わらない仕事に苛立ち、疲れ果てた俺は、誰にも言わずに早めに仕事を切り上げた。久々に早く帰れるというのに、家に戻る気力も湧かず、ただ街を彷徨うことにした。
いつもの喫茶店でコーヒーを飲みながらスマホをいじっていた時、ふと目に留まった広告。そこには「癒し」「ストレス解消」といった言葉が並び、派手ではないが、どこか誘うようなデザインが施されていた。オナクラ――派遣型のオナニークラブだ。少し躊躇したが、俺はその時、妙な衝動に駆られて店の名前をスマホで検索し、予約を入れていた。
案内された場所は、繁華街から少し外れたビルにあるレンタルルームだった。受付後部屋で少し緊張しながら待っていると、ノックと共に扉が開かれ、部屋に入ってきたのは、俺よりも少し年下の女性だった。
彼女の名前は「ナナ」と名乗った。24歳という若さを感じさせるが、その瞳にはどこか大人びた冷静さが宿っていた。俺が最初に抱いた印象は、落ち着いた雰囲気と、彼女の儚げな笑顔だった。彼女は何も強く主張せず、ただ淡々と自分の役割をこなすように見えた。
「どうぞ、楽にしてくださいね」とナナが優しく声をかける。
俺は少し戸惑いながら、指定された場所に腰を下ろした。緊張のせいか、体が少し硬直していたが、彼女は慣れた手つきで俺のそばに座り、手をそっと触れてくる。その瞬間、不思議な感覚が体を包んだ。これはただの肉体的な癒しだけではなく、心の疲れまで癒されていくような気がした。
彼女の動作は、まるで儀式のように静かで慎重だった。何も言葉にしないが、彼女の存在そのものが俺の中の張り詰めた糸を解していくようだった。ナナの手が俺の肩に触れ、彼女の目が俺を見つめると、心の奥底に潜んでいた孤独感が少しずつ溶けていく。
「普段、どんなお仕事されてるんですか?」
ナナの問いかけに、俺は少し考えた。答えるのが難しいというわけではないが、何となく自分の仕事について話すことが虚しく感じられたからだ。
「普通のサラリーマンだよ。毎日仕事に追われて、ただそれだけ。面白い話は何もないさ。」
俺は笑ってごまかしたが、ナナは頷きながらも、その言葉の裏にある何かを感じ取ったようだった。
「大変ですよね、そういうの。私も分かります、少しだけ。」
「君も大変なのか?」と、俺はつい訊き返した。彼女は笑顔を保ったまま、小さく息を吐いた。
「私たちの仕事も、色々あるんですよ。見えないところで…ね。でも、それが私の仕事だから、仕方ないって思ってます。」
その言葉は予想外だった。ナナはもっと無機質な対応をするかと思っていたが、彼女はどこかで自分の仕事に対する割り切りと葛藤を抱えているように見えた。
「こんなこと言うのは変だけど、君のような若い人が、こういう仕事をしているのが何となく信じられないよ。」俺は、つい本音を漏らした。
ナナは一瞬驚いた表情を見せたが、すぐにいつもの笑顔に戻った。「まあ、そうかもしれませんね。でも、お金が必要だから、働かないといけないんです。それに、この仕事しか今は選べなかったから。」
その言葉に、俺は胸が締め付けられるような感覚を覚えた。彼女は笑って話しているが、その背後には現実の厳しさが隠れているのだろう。彼女がこの仕事を選んだ理由や、日々感じる葛藤を想像すると、俺は自分の悩みがどれだけ小さく思えた。
「君だって、もっと他にできることがあるんじゃないか?」俺はそう言ってしまった。
ナナは少しだけ沈黙した後、小さく笑った。「そう思いたいです。でも、今はここが私の居場所です。現実は、そう簡単に変わらないんですよ。」
その言葉には、重みがあった。俺もまた、毎日仕事に追われ、現実に縛られている。お互いに、自分の人生をどこかで諦めている部分があるのかもしれない。彼女の仕事と俺の仕事、形は違えど、結局は同じような葛藤の中で生きているのだと感じた。
「それでも、何かを変えたいと思うことはあるだろう?」
俺の問いに、ナナはしばらく考えてから静かに答えた。「ありますよ。でも、変える勇気がないんです。怖いんです、失敗するのが。」
その答えに、俺は自分自身の姿を重ねた。俺もまた、変わることを恐れていた。新しいことに挑戦することも、自分の殻を破ることも、すべてが怖かった。そして、その恐怖が俺をここまで追い詰めていたのだ。
「俺も、君と同じだよ」と俺はポツリと呟いた。「毎日が同じで、変わることが怖くて、それでも変わらなきゃってどこかで思ってる。でも、その一歩が踏み出せないんだ。」
ナナは俺の言葉に耳を傾け、静かに頷いた。「人って、そうですよね。頭では分かっていても、なかなか動けない。」
俺たちは、しばらく無言で過ごした。部屋の静けさが、逆に心地よかった。ナナと一緒にいることで、俺は自分の中にある感情を見つめ直していた。彼女もまた、同じような思いを抱えているのだと思うと、不思議と孤独感が和らいだ。
「また、会えるかな?」
俺は、部屋を出る前にそう尋ねた。ナナは少し驚いた表情を見せたが、すぐに柔らかい笑顔を浮かべた。
「ええ、また来てくれたら嬉しいです。」
その言葉に、俺は少しだけ救われた気がした。仕事に疲れ切った俺にとって、ナナとの時間は短いながらも心の安らぎを与えてくれた。派遣型オナクラという特殊な場所での出会いだったが、彼女との会話は、単なる肉体的なサービス以上のものを感じさせてくれた。
それから数週間が経ち、俺は再びナナに会うためにその店を訪れた。彼女は以前と変わらず、静かで優しい微笑みを浮かべて俺を迎えてくれた。しかし、俺たちの間には、前回よりも少しだけ深い理解と共感が芽生えていた。
ナナもまた、変わりたいという思いを抱えながら、それでも現実に立ち向かいながら生きている。俺は彼女に何かをしてあげることができるわけではないが、少なくとも俺たちはお互いに支え合う存在になれた。
派遣型オナクラという出会いの場は、決して普通ではない。しかし、ナナとの出会いは、俺にとって特別なものであり、彼女との時間が俺の心を癒してくれた。俺は、彼女と共に歩む未来がどんなものかは分からないが、少なくとも今は、彼女と過ごすこの時間を大切にしたいと思っていた。
そして、俺は再び夜の扉を開けた。
上野の手コキオナクラで働くスタッフAがAIに手伝ってもらいながら作成してみますた